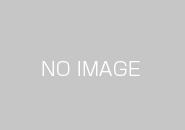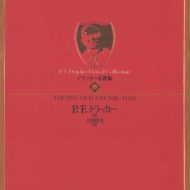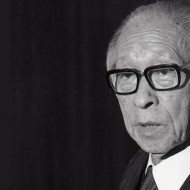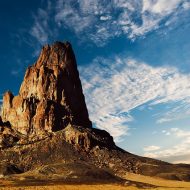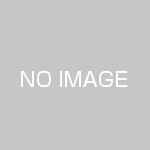平成30年、今年は明治維新から150年目である。
明治維新は戦死者は多くて3万人という極めて平和な革命であった。100万人を超えるフランス革命などとは桁が違う。
「政権をよこせ」と迫る薩長に「よかろう」と幕府がすんなり大政奉還に応じたのだから当然である。
もしも、武力で応じていれば、ヨーロッパの列強がこの紛争につけ込み、長引く戦争により多大な犠牲者が出たと推測される。徳川慶喜の決断はまさに歴史的英断である。
しかし、慶喜はなぜ、戦いを選ばず、大政奉還を受け入れたのか歴史学者の家近良樹氏によると、慶喜は有能であるが、家臣のことなど全く考えなかったらしい。
歴史の流れを正確に判断することはできたが、家臣には無関心であったと言う。新政府設立後の幕臣の悲惨な生活など思いもよらず、責任も感じなかったようだ。
もちろん、幕臣からも信頼されず、不人気なリーダーであった。
それに対して、西郷隆盛は部下思いで部下からも慕われ絶大な人気があった。
廃藩置県など新政府の方針や政策でで多くの部下や部下の家族が苦しむ姿を見て、先頭に立って政府と戦うことを選んだ。
新政府に反対する代表として最後まで戦い、結果として多くの戦死者を出した。(この死者が明治維新のほとんどの戦死者である)
現在、ITの進歩やグローバル化により、変化のスピードはますます加速している。
企業は変化する環境の中で生き残るため、拠点閉鎖、事業売却、配置転換などリストラを含めた改革は避けて通れない。
従業員からの信頼がなければ、経営はうまくいかないが、従業員の立場に偏りすぎると改革は進まない。
人望と改革を両立する鍵はコミュニケーション、話し合うことでしかないように思う。
元号がいくつ変わってもそれは変わらないだろう。
(山口伸一)